畳の大きさは関西と関東では畳の大きさが違います。
関西での畳の大きさは平安時代の寝殿造からきていると言われており、畳は身分の高い人が座る場所のみに使われていて大きさも950mm x 1900mmありました。
関東での畳の大きさを決めたのは織田信長で、彼が最初に用いた畳のサイズは900mm x 1800mmありました。これは鉄砲から身をを守るために作られたと言われており、なるほど・・・大体人間が入るサイズになっています。
時代劇なんかを見ていると忍者が畳の端を踏んで畳を立てて手裏剣から身を守る!!!
なんてシーンも実は織田信長考案の護身術の応用だったりします。
まあ、畳の端をどんなに強く踏んでも立ち上がらないですけどねっ!!!
ちょっと話がそれました(汗)
それらの理由から、関東、関西でそれぞれ畳の大きさが決まったわけですが、これに柱の寸法を考慮して
関西間1909mm x 954mm
関東間1757mm x 879mm
これが畳の寸法の起源となっています。
ちなみにタタミ!は「畳む」が語源です。
現在のように敷きっぱなしではなく、必要ないときは日の当たらないところに立てかけて焼けないようにしていたのです。それほど畳は貴重なものだったのです。
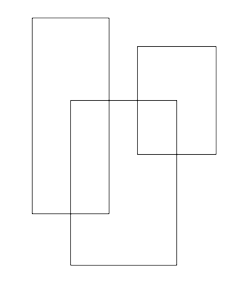
にわ
SECRET: 0
PASS:
記念すべきはじめてのコメントです^^
テラス屋根などもいまだに、関西間・関東間・メーターモジュールなどと三種類もあってややこしいですね・・・
起源やいわれをたどると雑学で面白いのでまた何か建築に関するネタをUPして行って下さい!
(分・尺・寸・間・坪とかも)
今度、輸入材の2×4(ツーバイフォー)等とかの材料規格寸法も何かの例を上げて詳しく説明して欲しいです!
ブログ頑張って続けて下さいね!!!
TASS Associates 一級建築士事務所
SECRET: 0
PASS:
にわさん
初コメントありがとうございます!
ずっと放置プレイが続いていたので嬉しい限りです!
リクエストもどんどん頂ければっ。